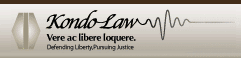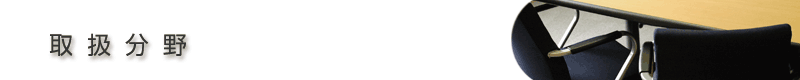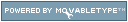大阪弁護士会所属 近藤総合法律事務所
大阪府大阪市北区西天満5-1-3 南森町パークビル6階 TEL06-6314-1630
戦略法務
新しい企業価値の創造を
コンプライアンス経営とは、一般的には「企業が、法律や企業倫理を遵守すること」を意味します。
ここ数年、倫理意識の欠如を原因とする企業の不祥事や、不芳情報などを内部に留め、貯めていく悪循環が、社会的問題として問題視されています。
これはつまり日本社会や市民が、企業が法律や企業倫理を遵守することの重要性、つまりコンプライアンスの重要性に注目しはじめたという事です。
近年の判例でも、企業倫理の重要性を判示したものは数多くあり、このことは、もはや、コンプライアンスは経営戦略の重要な要素であることを示唆しています。
また、適正かつ継続的な内部統制システムが構築されていること、「デュー・プロセス」(適正手続)の実践がなされていることは、単に企業側のリスク・コントロールという守りの体制であるだけに留まらず、“新しい企業価値の創造”とも言えます。
ただし、不祥事が生じてから、顧問弁護士や懇意にしている有識者を入れた調査委員会を設置するというやり方は、一時的な誤魔化しになる可能性があります。
企業の基本ガイドラインとして、業務に関しては、関係部署における適正な調査、検討がなされており、その検討結果が残されていること、また、会計や法律的判断に関しては、監査法人や顧問弁護士による外部のチェックを、日常的に受けていることが重要なのです。
企業改革を行っていくためには、真なる愛社精神と、弁護士などの外部専門家とともに継続的な企業改革を推進する情熱が必要なのです。
秘すれば花なり。秘せずば、花なるべからず。(世阿弥)
営業秘密(トレード・シークレット)とは、「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの」(不正競争防止法 2条1項4号)の事を言います。
日本は、情報立国とも呼ばれ、無形の“情報”が産業の中心となる、知財立国となりつつあります。
企業にとって情報や、独自のノウハウは資産であり、営業秘密とされ、例えば、製造業の場合、特許や商標権などは、産業財産権として保護され得るものですし、また、それらは、登録して保護されるものだけに限らず、企業の生産方法や販売方法、顧客情報なども、営業秘密に該当します。
これらの営業秘密は、競合他社に知られたり漏洩しないように防衛しなければ、企業にとって大きな潜在リスクとなることは明白です。
この情報資産という営業秘密を各自が守り、また、それを互いに侵害しないためのルール、法律にあたるのが、不正競争防止法です。
不正競争防止法は、事業者間の公正な競争を促すことを目的とする法律で、 営業秘密を不当に使用した場合、一定の要件で不正競争行為となり、不正競争防止法違反となります。
ただし、この不正競争防止法については、法律が、対象となる情報資産の運用・流用について、第三者的にその要件を満たしているか否かを判断するだけのものではありません。
企業側が、営業秘密を守るために、具体的管理と組織的管理をどのように行っているか、という社内管理体制のあり方についても判断される基準であることに留意しなければなりません。
インターネットの普及による高度情報化が進む中、企業と個人が相互に守られた形で、法的保護を受けるためには、そのための組織的管理体制の構築、あるいは専門知識をもってする、ノウハウの蓄積が急務といえるでしょう。
誰もが安心して情報化社会の便益を受けるために
平成17年4月1日、個人情報保護法が全面施行されました。
個人情報保護法とは、個人情報を取扱う事業者に対して、個人情報の取り扱い方法を定めた法律で、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的としています。
IT社会、ユビキタス社会(サイバースペース)の誕生により、情報の収集、分析、利用、加工、管理が容易となり、ボーダレス化した今、個人情報を取り巻く状況は、絶えず変化しています。
それは、個人情報(プライバシー)漏洩という、個人レベルでのリスクという側面を持つとともに、営業秘密等の流出の危険性増大など、企業を取り巻く情報セキュリティ面のリスクが増大したということでもあります。
また、個人情報の利用は、大きなリスクを伴う一方で、マーケティングや法的手続の行使にとっては不可欠であることから、この分野における社会の関心は高く、それは、一旦、この分野で事故を起こしてしまえば、企業側は直接的、間接的に、深刻なダメージを受けることになる、という事も示唆しています。
しかしながら、企業が情報漏洩に関する事故を起こした場合、行為態様や被害状況などは各事案ごとに様々です。また、実際には、事故発生後の慰謝料の金額そのものよりも、弁護士費用や訴訟遂行コスト(opportunity cost)の方が大きく、さらに信用(good will)毀損などがより重要な問題となっていることも事実です。
安全管理のために、必要かつ適切な措置を決めることは大変難しく、それを実装するためには専門的な判断が不可欠となりますが、企業側は、個人情報保護法を正しく理解し、管理規程の位置づけ、遵守する基盤を確立しておく必要があるでしょう。
従来、有体物である「物」についてしか認めれられていなかった特許について、近時、審査基準が改定されたことにより、無体物たるソフトウェアについても特許出願が認められるようになり、最近では、ソフトウェア関連発明ないしITに関する特許出願が増えています。
特許は、物造りのメーカーだけではなく、ソフトウェア企業にとっても、重要な問題となっています。
ソフトウェア企業にとって特許出願を行うことは、各種製品の開発プロセスで生まれるアイディア、着想、技術を会社の資産として保全するだけでなく、自社の将来の技術開発の障害とならない素地を作るとともに、競合他社に対する牽制や、あるいは、営業面での有用性があると言えます。
また、自社開発を行うのみではなく、他社に対してライセンスを行うことなどよって、より幅の広い多様なビジネスモデルを構築する上で不可欠となっています。
さらに最近では、自社のエンジニアによる発明だけでなく、開発委託企業との共同出願も増えてきており、様々な業種・企業との提携や共同開発に伴う共同特許出願も増えてくるものと思われ、そこでの紛争も予測されることから、秘密保持契約(NDA)の締結や共同開発過程における成果物の取扱などについて明確化するなどの、万全な予防法務が必要となっていると言えます。
今後は、出願する発明の戦略的価値や特許ポートフォリオについて検討しつつ、ソフトウェア技術に精通し、ベンチャー企業の特質を理解できる弁理士や弁護士との連携が不可欠になってきており、共に営業戦略、法務戦略について考えていくべき時代が来ていると言えます。
© Kondo Law Office All Rights Reserved.