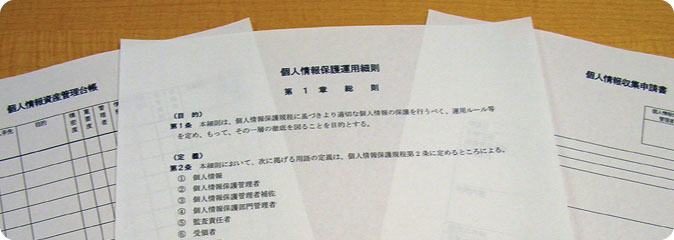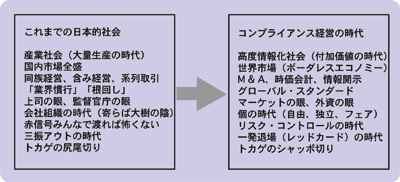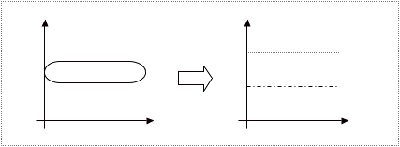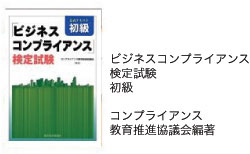1.コンプライアンス経営は、時代の要請
1) パラダイム・シフト
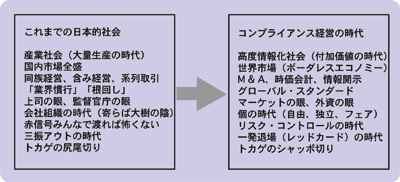
2)コンプライアンス経営に向けた企業改革
・「意識が変われば、考え方が変わる。考え方が変われば、取り組み方が変わる。取り組み方が変われば、当然結果が変わる。」(元阪神タイガース監督野村克也氏)
・企業改革は、いくつもの岩盤を突破しなければならないトンネル工事を行うようなもの。
a「現状認識拒否の岩盤」
悪い方向、悪い状況になっていることを否定する
b「誤った判断の岩盤」
改革する必要はないと安易に考える
c「絶望の岩盤」
理屈ではそうだが、実際には無理と思い込む
d「実行拒否の岩盤」
指針や計画だけを作って安心してしまう
e「継続拒否の岩盤」
改革を持続することを止めてしまう。
2.実践「法令倫理ガイドライン」
1)法令倫理ガイドラインの内容
2)法令倫理指針の活用
・「お題目」になっていてはダメで、じっくり踏み込んで考えておくべき
・不祥事、不芳情報をどんどん取り込んで、貯めていくシステムになっているか(法令倫理指針という骨に、日々、肉付けしていく体制は作られているか)。
・意味を充填された法令倫理指針がバイブルや詳細な危機管理マニュアルのようになり、全従業員にフィードバックされるシステムになっているか。
・ミスやトラブルをオポテュニティと呼べるカルチャがあるか?
・会社の憲法あるいはcredo(信条、哲学)として、尊重し、実践されるよう法や規則に魂が込められなければならない。「破くと血が出るような判決書」(某裁判官)
3.コンプライアンス経営の視点
1)近時の裁判例
a 長銀EIE訴訟(東京地裁平成14年7月18日、判時1794号131頁)
旧株式会社日本長期信用銀行が、株式会社イ・アイ・イーインターナショナルに対し、60億円の融資を行い、さらに、本件融資の期限延長を行ったことにつき責任追及を行ったものであるが、東京地裁は、メインバンク論を展開した上で、「本件融資は、時間的制約がある中で原告が訴外会社との取引の改訂で組織的かつ継続的に収集・蓄積してきた情報を関連部署において総合的に分析、検討した上、本件融資を行なう必要があり、債権保全措置をも勘案すると回収にも懸念はないとの結論に至ったものであり、その判断は、当時の具体的状況下においては、相応の裏付けを有するものであったというべきであり、本件融資が判端の前提となる事実認識及び判断の内容に裁量の範囲を超えた誤りがあったと認めるに足りる証拠はない」とし、責任を否定した。
b 大和銀行株主代表訴訟担保提供命令事件(大阪高裁平成9年12月8日、資料版/商事法務166号138頁)
いわゆる「システム構築責任」と呼ばれる責任を肯定した裁判例であり、大阪高裁は、「現在の株式会社において、代表取締役、業務執行取締役などの執行機関の支配が進む中で、これらを除くいわゆる平取締役は、業務執行というよりも業務執行監視義務を中心とした任務を負う。すなわち、取締役は、取締役会の構成員として、会社に対し、代表取締役、業務執行取締役ないしその下に行われる業務執行一般につき、これを監視し、必要があれば、取締役会を自ら招集し、あるいは招集することを求め、取締役会を通じて、その業務執行が適正に行われるようにする職責を有する。即ち、取締役は取締役会に上程された特定の業務執行に限らず、広く代表取締役ないし業務執行取締役の業務執行につき一般的監視の義務ないし任務を負うのである(最判昭48.5.22民集27巻5号655頁参照)」「このような不正行為を未然に防止し、またその損害の拡大を最小限にとどめるには、証券ディーリング業務担当者の行った取引を常時チェックする体制を整えることが必要不可欠である。すなわち、証券取引業務を行う会社は一般にその証券ディーリング業務担当者の行う事務を会社に対する証券取引の注文に限定している。そして、右証券取引の確認、同取引代金の支払、預かり証券の残高照合等の手続は、すべて証券ディーリング業務担当者以外の管理部門が行う。これらの手続に証券ディーリング業務担当者が関与することを禁止する。このようにしてチェック体制を整え、不正行為を未然に防止するべく努めているのである。すなわち、右のような内部統制システムの構築及び実施は,証券取引業務を行う銀行の業務執行取締役(後示のとおり平取締役及び監査役についても同様)にとって、その基本的な組織運営のあり方にかかわる重要な任務であるといえる。」「ところが、本件記録によると、大和銀行は、国際金融の中心地であるニューヨーク支店における証券取引業務を行うに当たり、同業務の危険性に配慮し、証券ディーリング業務担当者の不正行為等を未然に防止し、またそれによる損害の拡大を最小限にとどめるための前示チェック体制、すなわち内部統制システムを構築し、これを実施していたことを直ちに認めることができない」と判示した。
c ダスキン株主代表訴訟事件(大阪地裁平成17年2月9日)
「両被告は食品衛生法に違反して無認可添加物入り肉まんの販売を継続した」「添加物の混入を知りながら販売を決定、継続した」「消費者が混入を知れば会社の信用が損なわれ、多額の費用支出を余儀なくされる可能性があった」と認定し、元専務及び元事業本部長の注意義務違反を認め、株主による106億円の損害賠償請求を認めた。
2)「デュー・プロセス」(適正手続)の実践
・適正かつ継続的な内部統制システムが構築されていること
・関係部署における適正な調査、検討がなされており、その検討結果が残されていること。また、会計や法律的判断に関しては、監査法人や顧問弁護士による外部のチェックも受けていること。
ただし、不祥事が生じてから、顧問弁護士や懇意にしている有識者を入れた調査委員会を設置するというやり方は、一時的な誤魔化しになる可能性がある。
→cf.最高裁は、損害を被った企業による損害賠償請求事件において、調査委員会の調査報告書について文書提出命令を命じた(平成16年11月26日)。
・「リスク」そのものの存在がリスクなのではなく、「リスク」をコントロールできないこと(その主体性)がリスクである。
4.最後に
1)意識的法令遵守の時代へ
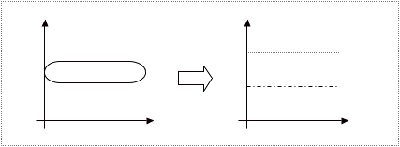
「法は最低限の道徳」(常識=法)
「法令遵守(形式知)と常識(暗黙知)」
2)経営判断原則(Business Judgment Rule)とコンプライアンス
企業経営者において、自由かつ広範な経営判断(裁量権)が認められているが、その経営判断原則も、違法(illegal)な行為には適用されないのは、外国においても日本においても裁判上確立されたルール → 法令違反は、致命的!
3)結びにかえて
一度や二度、本を読んだり、講演を聴いたりしても、人の意識や考え方は容易には変わりません。
企業改革を行っていくためには、真なる愛社精神と、弁護士などの外部専門家とともに継続的な企業改革を推進する情熱が必要と言えるでしょう。