1.改正の意義・目的
・「担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律案」平成15年7月25日成立、平成16年4月1日施行。
明治29年制定後、昭和46年の根抵当権新設以来の大改正。
・権利実現の実効性の確保、不良債権処理の促進
2.改正のポイント
1 担保法制に関する改正点
a)担保不動産収益執行の創設(民執180条2項)
b)抵当権消滅請求(民378条)
c)一括競売(民389)
d)短期賃貸借保護の廃止(民395)
e)根抵当権の元本確定(民398の19)(民398の20-1は削除)
f)雇用関係の先取特権(民308)(商295は削除)
g)債権質の設定における債権証書の交付(民363)
2 執行法制に関する改正点
a)差押禁止財産の範囲の拡張(民執131)
b)民事執行法上の保全処分の要件緩和と強化(民執55条等)
c)明渡執行における占有者特定の緩和(民執55条の2等)
d)間接強制の適用範囲の拡張(民執173)
e)財産開示制度の新設(民執196条以下)
f)養育費等の履行期前の差押え(民執151の2)
g)動産競売の要件緩和(民執190)
h)内覧制度の新設(民執64条の2)
3.担保不動産収益執行(新設)
1 意義
従来、担保権の効力は不動産の使用収益権能には及ばないという考え方があり、担保権の実行としては、強制管理(民執43条1項)の方法は認められていなかった。
しかし、バブル経済の崩壊による不動産価格の下落により、競売という方法では被担保債権全額の回収が極めて困難な状況となり、強制管理に類似した制度が新設された。
2 手続の流れ
・差押えと同時に管理人選任
(民執188,93-1,94-1)
・管理人において、賃料収受、契約締結、契約解除
(民執188,95-1,99)
・管理人または執行裁判所による配当実施
(民執188,107,109)
・強制管理においては、各債権者の債権額按分であるが、収益執行においては、担保権の順位に従って配当される
(よって、通常、第1順位の担保権者のみの配当となる)
3 物上代位との競合
・収益執行制度が新設されたが、賃料に対する物上代位の手段は排除されていない。
・手続としては収益執行が優先し、債権執行手続の効力が停止され、物上代位者は配当要求を行うことになる(民執93の4)
・一般の先取特権者の配当要求可(民執105)
・他の抵当権者は、収益執行申立てをしなければ、配当を受けられない(民執107-4一ハ)いわゆる二重開始決定を得なければならない。
4 実務の指針
・ 配当サイクルは、3〜4ヶ月程度と見込まれる。
・ 管理人の資格については法律上の制限はなく、信託会社、銀行、不動産会社その他の法人も管理人となり得る(民執法94条1項、2項)
・ 大阪での強制管理の例では、回収した賃料の5%(月額30万円程度)を月額報酬とした例がある。
・ 大規模物件でテナント数が多いあるいはテナントの入れ替わりが激しい、第三債務者の特定が困難なケース、所有者が反社会的勢力であり管理権限を奪う必要がある場合などに限られるか。
4.抵当権消滅請求(「滌除」からの衣替え)
1 図解
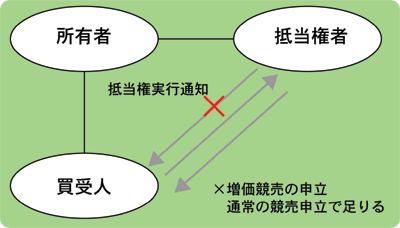
2 改正内容
・請求権者(民378)抵当不動産につき所有権を取得した第三者に限定
・請求可能時期(民382)抵当権の実行による差押えの効力が生ずるまで
・抵当権実行通知義務(旧民381,387)の廃止
・増価競売(旧民384)の廃止
・請求を受けた時から、2ヶ月以内に通常競売(民384一)
・取下げ、却下、取消しによる承諾擬制(民384二〜四)
但し、民執63条3項の無剰余取消の場合、68条の3のいわゆる「三振アウト」の場合には、取消の効果が発生するものの、承諾擬制の効果は生じない
・回収制限はなく、何度でも抵当権消滅請求が可能と解される。
3 ケーススタディ
担保不動産の買い受けを希望する顧客がいるので任意売却をしたいが、後順位の抵当権者が抵当権の抹消になかなか応じようとしない。そこで、顧客に対して所有権移転登記を行い、顧客が抵当権消滅請求を行うという方法如何。
5.短期賃貸借保護の廃止
1 改正の趣旨
抵当権設定後の賃貸借がすべて抵当権者に対抗できないとすると、抵当権設定後において賃借人を見つけることが容易ではなくなり、不動産所有者の使用収益権の発揮が難しくなるとの観点から、短期賃貸借保護の制度が設けられていた。しかし、執行妨害の目的のため悪用される例が後を絶たず、また、短期賃貸借の更新時期と競売による差押時期との先後や期間満了時と代金納付時期の先後によって短期賃貸借が買受人に引き受けられるか否かという違いも生じ、うまく機能していなかった。
2 改正の内容
・抵当権者に対抗できない建物賃貸借により、競売手続開始前から使用・収益している建物使用者等は、買受人の買受の時から6ヶ月は引渡をしなくてもよいこととなった(民395)
・もっとも、これらの者でも買受人から催告を受け、相当の期間内に1ヶ月以上の使用の対価を支払わない者については、明渡猶予期間は認められない。
・明渡猶予期間が認められる建物賃借人に対して、買受人は、6ヶ月間は引渡命令を受けられないことになる。
・猶予期間中は、賃貸借関係は生せず、一般的には不法占有と解説されている。
3 抵当権者の同意による対抗力付与
(民387)
・抵当権の登記後に登記した不動産賃貸借は、優先する総ての抵当権者による同意を登記すれば、同意した抵当権者に対抗できることとなった。
・区分所有建物の登記がなされていない賃貸ビルなどでは、建物全体に転貸許可特約付きでの賃貸借登記をするなどの工夫をしなければ利用できない問題がある。
・例えば、賃借会社の株主が反社会的勢力になるなど事実上の事情変更が生ずる場合を考えれば、抵当権者が同意するリスクは否定できない。
・担保不動産価格の相当な減価要因になると思われる。
4 旧法下との比較
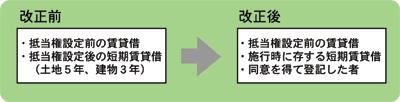
5 実務の指針
・短期賃貸借保護の廃止によって、抵当権の登記後の賃貸借は抵当権者に対抗できないこととなったが、担保不動産を任意売却する際には、当然に抵当権登記後の賃貸借が排除できることにはならず、敷金返還請求権も当然に排除されるわけではない。
・短期賃貸借の制度が廃止されたことにより、継続的な使用を考えて既に抵当権設定登記がなされている建物を新しく賃借する場合には、賃貸人の後日の経済状態の変化によっては、予定外の時期に建物を明け渡さざるを得ない上に、差し入れた敷金の返還も期待できないという不測の事態が生じる可能性がある。
6.内覧制度(新設)
1 手続の流れ
執行手続において、買受希望者を競売不動産に立ち入らせ見学させる手続。
差押債権者の申立てにより執行裁判所が命令し、執行官が実施(民執64の2)
従来は、1現況調査報告書、2評価書、3物件明細書を競売記録やインターネットにより閲覧・謄写することによって物件の情報を得る他なかった。
2 内覧の実施
執行官は、内覧実施命令があったときは、遅滞なく、内覧への参加の申出をすべき期間及び内覧を実施する日時を定め、これらの事項及び不動産の表示を広告し、かつ不動産の占有者に対して内覧を実施する日時を通知しなければならない(規則51条の3)
3 実務の指針
・買受希望者は、差押債権者に対して内覧の申立をして欲しいという要請を行うことが考えられる。他方、差押債権者の立場としては、競落可能性、希望の理由、物件の性質、占有者の実態、申立のコスト(内覧実施の基本手数料は2万円であるが、補助者の費用等相当額が必要になる)などを考え、対応することとなろう。
・占有者とのトラブルや競売ブローカーによる談合あるいは威迫行為によって買受希望者の入札意欲がわせることも考えられるので、注意が必要。
7.債務者財産開示制度(新設)
1 手続の流れ [別紙参照]
裁判所が債務者を呼び出し、債務者に自己の財産について陳述させる手続。
2 制度の内容
・管轄 債務者の普通裁判籍所在地の地方裁判所
(民執196)
・申立権者
(民執197)
執行力ある債務名義の正本を有する金銭債権者(但し、未確定判決、支払督促、公正証書は除く)、一般の先取特権者
・要件
1-強制執行等の不奏功または不奏功が確実であること
2-債務者が3年以内に財産開示をしていないこと(例外あり)
・期日
申立人と債務者を呼び出す
(民執198)
裁判所のほか、申立人に質問権
(民執199-3,4)
非公開(民執199-6)
宣誓
(民執199-7、民訴201-1)
・記録閲覧
(民執201)
・情報の目的外利用の禁止
(民執202)
3 実務の指針
開示義務者の不出頭、宣誓拒否、陳述拒否、虚偽陳述の場合、過料の制裁(民執206)がなされることになっているが、そのサンクションは30万円以下の過料に過ぎないことから、その実効性には疑問がある。
[参考文献]
・季刊「事業再生と債権管理」別冊No.2「改正 担保・執行法の実務」谷口園恵他編、きんざい(\3,439+税)
・旬刊金融法務事情1700号「施行直前!改正担保・執行法Q&A」中務嗣治郎監修
・銀行法務21 No.624「担保・執行法制の改正と実務への影響」経済法令研究会



