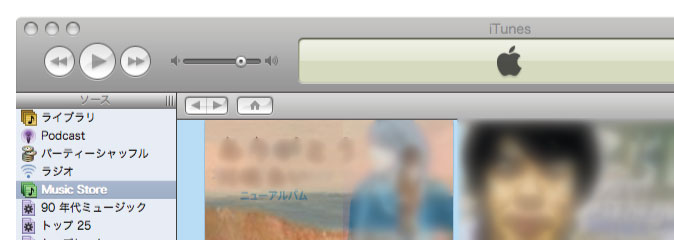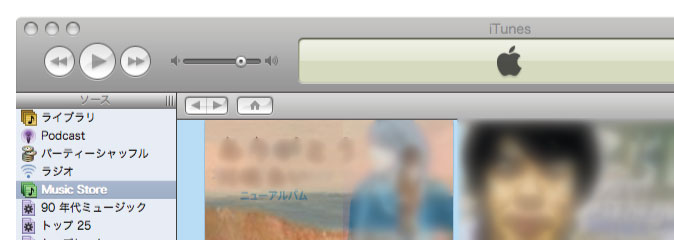1. はじめに
今日、Web取引において、ソフトウェアや音楽(MP3)データなどのデジタルコンテンツ(無体物)に関する取引が頻繁に行われており、2002年7月、経済産業省より「電子商取引等に関する準則」も公表されている。そこで、今回は、主に無体物たる情報財取引特有の問題点について検討してみたい。
なお、特定商取引に関する法律の施行に伴い、同法の適用対象に「プログラムを役務の提供を受ける者の電子計算機に記録し又は記録させて、使用させること」や、「映画、演劇、音楽、スポーツ、写真又は絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞させ、又は観覧させること」も指定役務として追加されたことから、特定商取引に関する法律の適用を受けることになっている。
2. 情報財取引に関する米国での従来の議論
1) シュリンクラップ契約(shrink-wrap licence)
・ProCD事件判決 (ProCD v. Zeidenberg, 86F.3d1447(7th Cir.1996))
パッケージの外箱に使用許諾の契約条件内容が記載されていなくても、契約条件が通常の契約法における無効な内容でない限り、シュリンクラップ契約は有効であり、連邦著作権法もシュリンクラップ契約の有効性を妨げない(いわゆる「専占」(preemption)の問題)
・もっとも、シュリンクラップ契約の成立時期については各説あり。
a 契約が店頭売買の時に成立するとする立場
b パッケージを開封し、内容を確認する機会が与えられたにもかかわらず使用した時に成立するとする立場
c 契約成立は店頭売買の時であるが、シュリンクラップ契約の内容が契約条項となるのはその内容を検査する機会が訪れた時であると解する立場
2) クリック・オン・ライセンス(Click-on License)、クリックラップ・ライセンス
・メーカー(ウェブ開設者)とエンドユーザーの間で直接に契約が成立
・制作者とエンド・ユーザーが直接取引を行う『クリックラップ』な電子商取引では小売店の介在した現実社会における『シュリンクラップ』契約以上にライセンサーの支配が強まる」という指摘
・公共政策(public policy)の観点から是認できないような場合には、ライセンス・ミスユースの問題も生じうる
・クリックラップ契約を有効に成立させるための要件
a.電子商取引も含めて、商品が最初に使用される前(または、支払い義務が生じる前)に、詳細なライセンス条項を買主またはユーザーに開示すること、例えばハイパーリンクでライセンス条項の文言を表示できるようにしておくこと
b.もし買主がライセンス条項への同意を拒絶する場合には、代金(およびその他の経費)を返還するように申し出ておくこと
c.買主が商品を使用する前に、ライセンス契約への同意を明確に表明させるように「同意する」の欄をクリックさせたり、「同意します」とタイプさせること
d.クリックラップ契約の中に業界の慣行から逸脱するような条項が含まれている場合は、契約に同意させる前にその部分を特に目立たせること
3) 米国統一コンピュータ取引法(UCITA)
イ) 米国の立法動向
・当初のUCC2B(米国統一商事法典第2B章)のドラフトにおいて、ソフトウェア・ライセンス、アクセス・ライセンス、情報一般のライセンスを含めた契約法として審議
・コンピュータ情報取引に限定
・ 映画、録音、放送のコアビジネス及び新聞、雑誌、書籍等の印刷物は、UCITAの適用範囲外
・1997年7月のNCCUSLの総会におきましては、UCITAとともに、統一電子署名法(The Uniform Electronic Transactions Act)も採択
・UETAは、紙がなくても、代わりに電子記録でも取引は成立することを明文化して いるが、「みずからは契約法であることを止め(契約の有効成立等の問題は契約法一般に委ね)、いわば電子法に徹している
・UCITAは、ソフトウェア・ライセンス・アクセス・ライセンス、情報一般のライセンスを含めた契約法一般について、多岐にわたる様々な規定を設けている
ロ) 準拠法
・コンピュータ情報取引契約に関する準拠法について、UCITAは、次のような段階的な規定を設けており、特徴的なルールを定めている
(a)契約自由の原則により、当事者の合意に基づき準拠法を選択することが可能とされている。ただし、消費者契約については例外があり、合意に基づき選択されたとしても、当事者間で準拠法の取り決めがない場合に以下の(b)と(c)の規定によって適用される法律の下で認められない場合には、その選択は無効となる。(第109条(a)項)
(b)
ア:アクセス契約またはコピーの電子的引渡にかかる契約であるときは、契約締結時のライセンサー所在地の法律
イ:それが「有形媒体(tangible medium)上のコピーの引き渡しの消費者契約」であるときは、その消費者へのコピーの引渡の地の法律
ウ:その他の場合には、その取引(transaction)にもっとも関係が深い地の法律(第109条(b)項)
(c)上記(b)の規定に基づく場合、その適用される法域が米国外となる場合は、その地にUCITAの規定と実質的に同じ保護と権利を与える場合でない限り、米国法が適用される。(第109条(c)項)
(d)所在地を定める基準は、一つの営業所をもった当事者であれば、その営業所の所在地、二つ以上の営業所をもった当事者であれば、その主たる執行事務所(chief executive office)、物理的な営業所がない当事者については、その法人なりした、または当初の設立地、その他の場合は実際に住んでいる居所とする。(第109条(d)項)
・すなわち、無条件に当事者自治の原則を定めているのではなく、その取引の内容に応じて最も密接な関連法を選択するというルールを採用した上で、消費者保護立法の適用という属地的適用にも配慮しており、ライセンサー側とライセンシー側のバ ランスをとった規定になっている
ハ) 裁判管轄
(a)当事者間で専属管轄を定めることが不合理かつ不適当(unreasonable and unjust)でなければ、専属的管轄を定めることができる。(第110条(a)項)
(b)裁判管轄の取り決めについては、契約上明示的に規定されていない限り専属的ではない。(第110条(b)項)
・この裁判管轄については、準拠法合意の場合と同様、契約書をドラフトする側、すなわちライセンサーが自らの所在地を管轄する裁判所を選択する場合がほとんどであり、ライセンシーにとって不利であるという指摘もあり
ニ)マスマーケット・ライセンスの要件及び効果
・どのような場合に契約の拘束力を認めるべきであるのかが問題
・UCITA第211条
(a)情報の使用中もしくは使用前、又は情報へのアクセス前に「同意の表明(manifestingassent)」等により当該マスマーケット・ライセンスに合意すること。
(b)仮に当事者により採用された条件であっても、当該条件が第111条に規定された「非良心的(unconscionable)」な条件でないこと、又は第105条(a)(b)に規定された連邦法に専占(preempted)されず又はパブリック・ポリシーに違反しないこと。
(c)当事者の明白な合意事項と争いがないこと。
ただし、(a)の「同意の表明」を行うには、「吟味の機会」(opportunity to review)が必要とされている(第112条)。
・契約の不成立の場合、以下の権利
ア:支払った対価の返金
イ:情報の複製物を返却又は破棄するのに要した費用の返済
ウ:情報のインストールによって生じたライセンシーの情報処理システムの変化を従前の状態に復帰させるために要する合理的な費用。ただし、ライセンスの内容を検討するために、情報をインストールする必要があったこと及びその情報のインストールにより、ライセンシーの情報処理システムが変化し、情報を削除しても従前の状態に復帰できないことが条件とされています。
ホ)電子契約の成立要件
・米国詐欺防止法(Statute of Frauds)では、500ドルを超える商品の売買契約については、当事者の署名のある契約書を作成することが契約の成立要件であるとされている
・UCITAにおいては、詐欺防止法の適用を排除した上で(第201条)、500ドルを超 える電子商取引の成立要件について、書面に代わる新しい「記録」(Record)という概念を定義
・署名の代わりに、署名を含む広い概念として、「本人認証」(Authentication)概念を採用(第102条6項)。
・「電子代理人」(Electronic agent)に関する規定(第206条)
ヘ)アクセス契約
・アクセス契約とは、他者の情報処理システムへの電子的なアクセスを行うこと、若しくは当該システムから情報を得ること、又は、当該アクセスと類似する行為を行うことであると定義(第102条(a)項の(1))
・アクセスの切断に関しても免責規定(第611条(b)項)
ト)電子的自力救済
・電子的自力救済(self-help)とは、ライセンシーが契約違反を行い不正にソフトウェアを利用している場合、あらかじめ内蔵させていたプログラム等により、直ちにそのソフトウェアの使用を不可能にし、または破壊してしまうこと
・電子的自力救済を行うためには、電子的自力救済の使用を認める契約条件についてライセンシーが明白な同意を表明している必要があり、ライセンサーは、電子的自力救済を行う前に、それを行う旨を15日以上前に、磁気、対象となる違反の内容 及び抗弁がある場合のライセンサーの連絡先を記載して、ライセンシーに通知しなければならない
・ ただし、第三者に損害を与える場合には、電子的自力救済の行使は認められない
3. 「電子商取引等に関する準則」(経済産業省)
・「電子商取引等に関する準則とその解説」(商事法務 別冊NBL No.73 \3,360)
1) ライセンス契約の成立
・ライセンサー(ベンダー)がライセンシー(ユーザー)に対して、情報財を一定範囲で使用収益させることを約し、ライセンシーがこれに同意することによって成立する契約をいう。
・「ライセンス契約の内容を認識し、契約締結の意思をもってクリックした場合は、ライセンス契約が成立(民法第526条第2項)しているため、不同意を理由とした返品は認められない。」
cf.電子契約法3条、民法95条
・「当該情報財を使用することについてライセンス契約による格別の条件を付さず、情報財をダウンロードすることによってユーザーは情報財の複製物の所有権を有することを目的とする契約を締結したものと解される。」(P.92)
←複製物の所有権を取得すると言えるか?
「オンラインによる契約画面上、ライセンス契約締結の必要性が明示されている場合は、原則として、ユーザーに対して情報財を提供(送信)するとともに当該情報財を一定範囲で使用収益させることを内容とする契約、すなわち、ライセンス契約に情報財の提供(送信)が付加された契約を締結することになると解される。」(P.93)
←通常のライセンス契約との対比で考えると、情報財の提供(送信)は単なる履行方法を定めたに過ぎないと考えられるのではないか?
2) 重要事項不提供の効果
・民法1条2項の信義則により、契約の締結に当たっては、契約の一方当事者に、相手方に対する一定の情報提供の義務が課されると解されることがあり、その義務を履行しなければ、相手方は契約を解除することができる可能性がある。
・ユーザーが代金を支払ったにもかかわらず動作環境が明示されなかったため情報財を使用することができない場合は、提供契約やライセンス契約の解除という形でユーザーの保護が図られる可能性がある。具体的には、OSの種類・バージョン、CPUの種類及び演算速度、メインメモリの容量、ハードディスク容量など。
3) 契約中の不当条項
イ) 公序良俗に反する契約条項
←例えば、民法572条(担保責任を負わない旨の特約によっても免責されない場合)などの趣旨も含めて考えるべきではないか。
ロ) 消費者契約法(第8条〜10条)に違反する契約条項
全部免責規定、故意又は重大なる過失がある場合の一部免責規定は、無効(8条1項)。
ただし、代物提供又は瑕疵修補義務を負う場合は、例外(同法2項)。
ハ) 競争制限的な契約条項
ex.リバースエンジニアリングを禁止することにより、市場における公正な競争を阻害するおそれがある条項
←どういう場合か?
ニ) 著作権法上の権利制限規定がある部分についてユーザーの利用制限を課している契約条項
「著作権法第30条から第49条の規定は、法律で著作権を部分的に制限している(すなわちユーザーに対してその部分の利用を認めている)規定であるが、これらの規定は基本的には任意規定であり、契約で制限することが可能であるとの解釈がある。しかしながら、ユーザーに対してそれらの規定よりも利用を制限しているライセンス契約の条項は無効であるとの解釈も存在している。」
←著作権法において、著作権者と利用者の双方の利益をバランシングしているのであり、例えば私的使用のための複製の規定(著作権法30条)などは、「公序」(あるいは米国でいう「public policy」)と言える強行法規(条項)と考えるべきではないか?
4) 契約終了時のユーザーの義務
・ベンダーの履行遅滞(民法541条)ないし履行不能(民法543条)によって、契約解除を行う場合、そもそも無体物である情報財は返還(占有移転)を観念することができないとも考えられるため、民法第545条の原状回復義務の具体的内容が問題となる。
・ライセンス契約解除に伴う原状回復義務として、ユーザーは情報財の使用を停止しなければならず、これを担保するために、ベンダーはユーザーに対して情報財を消去するよう求めることができると解するのが合理的である。
Cf.著作権法第47条の2第2項「プログラムの複製物の所有者が当該複製物について所有権を有しなくなった後には、その者はその他の複製物を保存してはならない」
←あまり現実的ではなく、逆に言うと、情報財を返品する手続きは不要ということ?
・不当利得の点に関しては、ベンダーには損失がないと考えられる可能性もある。
「民法第703条の不当利得返還義務そのものの内容に当たらない場合は、少なくとも同条を類推適用して、・・・ベンダーはユーザーに対して、当該情報財を全て消去(削除)するよう求めることができると解するのが合理的である。」(p.104)
←著作権法114条 (損害の額の推定等)
ア:著作権者、出版権者又は著作隣接権者が故意又は過失によりその著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、当該著作権者、出版権者又は著作隣接権者が受けた損害の額と推定する。
イ:著作権者又は著作隣接権者は、故意又は過失によりその著作権又は著作隣接権を侵害した者に対し、その著作権又は著作隣接権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額を自己が受けた損害の額として、その賠償を請求することができる。
ウ:前項の規定は、同項に規定する金額をこえる損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、著作権又は著作隣接権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。
5) 契約終了の担保措置
・以下の3条件が揃っていれば、自力救済には当たらない可能性が高い。
ア:ベンダーとユーザーの間にそのような技術的制限手段が行われることについて事前に合意があること
イ:それが情報財の使用の継続を停止する範囲にとどまる技術的制限であること
ウ:当該技術的制限手段が事前に施されたものであること
6) ベンダーが負うプログラムの担保責任
・ 目的物たるプログラムが、取引の通念に照らし合理的に期待される通常有すべき機能・品質を有していない場合は、原則として、瑕疵に該当する。
・ 民法415条により、修補請求又は代物請求が可能と解されるが、通常すべてのプログラムが同一の品質と考えられるため、代物請求は不可能。また、個別的に修理等を行わないといけない有体物とは異なり、比較的容易にプログラムの修正を行うことができる。
・ 実務的には、例えば、MS-dosのように、当該プログラムのサポートが終了していることが多い。
・ ユーザーが消費者である場合、消費者契約法10条により、消費者に対して著しく不利益となる条項は無効となる。
・ 「瑕疵担保責任(民法570条)が問われる場合は瑕疵を発見したときから1年(民法566条)、債務不履行(民法415条)が問われる場合は引渡から10年(民法167条1項)であるが、通常はベンダーは事業者であるので商法の規定が適用され引渡から5年(商法522条)」
・新しいバージョンによる不具合のケースにおいて、旧バージョンを使うというダウングレードによる対処法についても、そのライセンスポリシーについては、各社によって考え方が異なる。