1.倒産処理の種類
事業を行っている法人や個人事業主が過大な借金を背負い、資金繰りに窮した場合、法的な倒産処理手続により事業の再建を図ることができます。
この点、倒産処理手続は2つの側面からの分類が可能です。
まず、手続の観点からは、裁判所へ申立を行う手続か否かにより、法的整理と私的整理に分類されます。
次に、目的の観点からは、事業を継続するか否かにより、再建型と清算型に分類することができます。
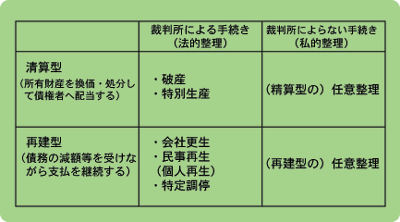
2.民事再生
民事再生とは、裁判所の再生開始決定を受けて、債権者の債権届出の結果をもとに債務者が債務の減額と支払条件の変更を主な内容とする再生計画案の提出を行い、債権者による決議と裁判所の認可決定を経て債務の圧縮を図るという再建型の倒産手続であり、個人・法人を問わず申し立てることが可能です(民事再生法21条)。
民事再生のメリットは、再生開始決定後も従来の経営陣(事業者)が経営を続けることができること、再生開始決定から再生計画の認可までの期間が比較的短く(6か月〜1年程度)手続が迅速であること、などが挙げられますが、一方で、抵当権などの担保権(別除権)の行使が制限されないため債権者から担保不動産の競売申立てを受けるおそれがあることや、現経営陣が退陣することなく大幅な債務の減額を求めるという提案が多いことから、債権者の同意が得られない場合がある、などのリスクもあります。
3.会社更生
会社更生とは、裁判所の更生開始決定を受けて更生管財人が就任し、負債の減額や不採算事業の整理などを経て会社の再生を図るという再建型の倒産手続であり、申立ができるのは、法人のうち株式会社に限られます(会社更生法1条,17条)。
会社更生においても、民事再生と同様に会社経営そのものは従来どおり継続されますが、更生開始決定後の会社の経営は裁判所から選任された更生管財人が行うため、従来の経営陣が経営に関与することは通常ありません。また、民事再生と比較して手続がより厳格かつ複雑となっており、終了までに長期間(早くても2〜3年)かかります。
ただし、会社更生は手続の公平と公正を図ることが重視されており、中小企業よりも、多数の債権者が複雑に関与する大企業の企業再生に適した手続といえます。
4.破産・特別清算など
破産とは、裁判所の破産開始決定を受けて破産管財人が就任し、その所有資産(不動産・動産・債権など)を処分・換価して債権者へ配当するという清算型の倒産手続です。債権者から申し立てる「債権者破産」もありますが、現状では、多額の債務を負担している債務者から申し立てる「自己破産」の方が圧倒的に多くなっています(破産法15条)。
特別清算とは、清算手続中の株式会社が清算の遂行に著しい支障が生じた場合や、債務超過の疑いがある場合に利用される手続です(商法431条、新会社法510条)。
この中でも特に破産について説明すると、破産においては破産開始決定時に所有していた財産は全て破産管財人が処分することになりますので、破産開始決定を受ければ事業を続けることができなくなります。
また、特に中小企業の場合、金融機関から融資を受ける際にその経営者(代表取締役など)が連帯保証人になっている場合が多いため、中小企業が自己破産を申し立てる場合、多くの場合法人と経営者が同時に自己破産を申し立てることになります。
破産の場合、会社を破産させた経営者は失格の烙印を押され、もう一度事業をやり直すことができないと考える人も多いようです。しかし、破産に至った原因が経営者の能力不足や乱脈経営などにある場合は別として、破産手続終了後に、個人営業あるいは別会社を設立して再起を図ることは不可能ではありません。会社の設備や財産は破産により処分されてしまいますが、経営者自身が培ってきた経営のノウハウや人脈は、破産しても経営者の「財産」として残るからです。現に、ベンチャー企業などの経営者には、過去に破産した経験がある人も決して珍しくはないのです。
なお、現在の商法には、株式会社が支払不能または債務超過のおそれがある場合に利用される会社整理という手続も規定されていますが(商法381条)、民事再生法が施行された現在は全く活用されておらず、改正された新会社法では廃止されることとなりました。
5.特定調停
特定調停とは、「特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律」(特定調停法)に基づく手続であり、経済的に破綻するおそれのある個人または法人が、債務の弁済のために調停の手続により債権者との利害調整を図るための制度です(特定調停法3条)
特定調停のメリットは、弁済案を債権者の多数決で決定する民事再生とは異なり、債権者と債務者が話し合いの結果合意に至るというプロセスを踏むため、倒産に至らずに債務の整理を行うことが可能な点にあります。
一方、特定調停は、制度として全債権者間の利害関係の調整を念頭に置いてはいるものの、解決方法としては調停、すなわち個別の話し合いによる解決が前提となる以上、基本的に債権者全員に調停案へ合意してもらう必要があります。例えば、民事再生では、再生計画案に反対する債権者がいても賛成する債権者が多ければ多数決により再生計画案が認可されるのに対し、特定調停では、調停案に反対する債権者が多ければ、結果的に企業の再建が頓挫する危険もあります。
以上のことから、特定調停は、大口債権者などの有力な債権者との間では弁済案の合意がほぼまとまっており、少数の反対する債権者との利害調整が残されているような場合に有効な手続とされています。
6.任意整理
任意整理とは、上記のような裁判所の手続によらず、企業と債権者との間で個別に話し合いを行い、和解の方法により債務の整理を行うものです。事業を終了して残った財産を処分して債権者へ配当する清算型の任意整理と、事業を続けながら債務の圧縮や返済期間の延長などの合意を目指す再建型の任意整理があります。
任意整理では、多くの場合弁護士が債務者の代理人に就任し、弁済案を債権者へ提示して個別に和解解決を図ることになります。
任意整理のメリットは、裁判所を通じた手続ではない分、簡易かつ迅速に処理が行えるという点にあります。また、債権者にとっても、民事再生や破産では裁判所へ予納金を納める必要があるのに対し、任意整理ではこの部分を債権者への配当原資とすることができるという意味で、結果的により多くの回収が図れる場合も多いでしょう。
しかし、任意整理はあくまで債権者との合意による解決であるため、弁済案が大口債権者や担保付き債権を有する債権者から理解を得られない場合には、交渉が難航することも多く、すべての事案で成功するわけではありません。
7.最後に
以上のように、事業を営む個人や法人がその債務の整理を行う場合、さまざまな方法があるわけですが、最も大切なことは、「事業を再建したければ、深刻な事態になる前に法的整理または任意整理の決断をすること」です。
資金繰りのために借金を重ねた結果、弁護士が相談を受けた時点で既に破産しか選択肢が残されていないといった事例や、民事再生手続を選択して再生計画が認可されても、計画通りの支払ができず破産せざるを得ないといった事例も往々にしてありますので、早い段階で弁護士などの専門家のアドバイスを受けることが大切です。



