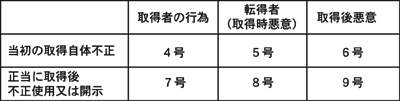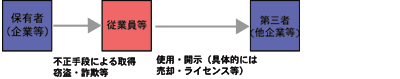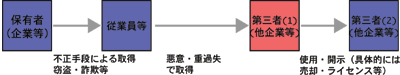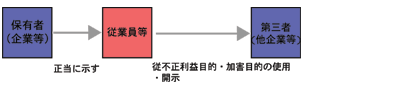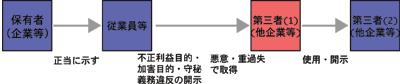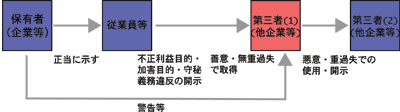1.営業秘密の民事的保護
1)「営業秘密」とは
「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの」(2条1項4号)
a)秘密管理
(従業員、外部者から、認識可能な程度に客観的に秘密の管理状態を維持していること)
具体的には、
ア)当該情報にアクセスした者に当該情報が営業秘密であることを認識できるようにされていること(「マル秘」「部外秘)(客観的認識可能性)
イ)当該情報にアクセスできる者が制限されていること(アクセス制限)
b)有用性(事業活動に有用な情報であること)
有用性については、例えば、保有することにより経済活動の中で優位な地位を占めることができるような情報であること。そして、ネガティブ情報と呼ばれる失敗に関する情報など潜在的な価値のある情報や、将来の事業に活用できる情報なども含まれる。
c)非公知性(公然と知られていないこと)
非公知性は、既存の書籍、雑誌、学会発表等から容易に引き出せない情報であることである。
2)「営業秘密」に係る不正競争行為類型(改正前)
(1) 当初の取得自体不正(4号から6号)
(2) 正当に取得後不正使用又は開示(7号から9号)
それぞれについて
a)取得者の行為(4号又は7号)
b)転得者の行為
ア)転得当初から悪意(5号又は8号)
イ)転得当初は善意だが転得後に悪意に(6号又は9号)
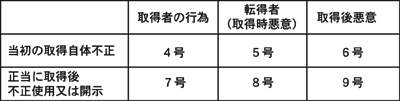
3)概念の説明
(1) 「不正取得行為」=窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為
印刷会社の従業員が会社の保管する大口受注報告書等の機密文書を持ち出して窃取し、企画調査業者に交付した事例(東京地判昭和40・6・26)
(2) 「保有者」=営業秘密を保有する事業者(7号)
企業に所属する従業員が職務上営業秘密を開発した場合に、本源的保有者は企業か従業員か。
「(各)実体法の理念に照らして個々の営業秘密の性格、当該営業秘密の作成に際しての発案者、従業員の貢献度等、作成がなされる状況に応じてその帰属を判断」(通商産業省知的財産政策室監修「営業秘密」87頁)
もし、従業員に帰属することになると、同業他社に転職して開示しても不正競争防止法違反にならないことになる(就業規則や個別契約で対応しておく必要)。
(3) 「不正開示行為」
=7号に規定する場合において同号に規定する目的でその営業秘密を開示する行為又は秘密を守る法律上の義務に違反してその営業秘密を開示する行為
「不正」=信義則上の義務に違反。契約違反が典型。ただし、契約締結準備段階や契約終了後もありえる。
4)営業秘密に係る不正競争行為の整理(改正前)
(通商産業省知的財産政策室監修「逐条解説 不正競争防止法」49頁以下参照)
2条1項4号類型
窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為(以下「不正取得行為」という。)又は不正取得行為により取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為(秘密を保持しつつ特定の者に示すことを含む。以下同じ。)
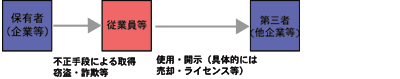
2条1項5号類型
その営業秘密について不正取得行為が介在したことを知って、若しくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得し、又はその取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為
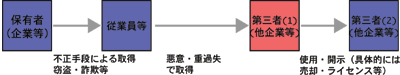
2条1項6号類型
その取得した後にその営業秘密について不正取得行為が介在したことを知って、又は重大な過失により知らないでその取得した営業秘密を使用し、又は開示する行為

2条1項7号類型
営業秘密を保有する事業者(以下「保有者」という。)からその営業秘密を示された場合において、不正の競業その他の不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、その営業秘密を使用し、又は開示する行為
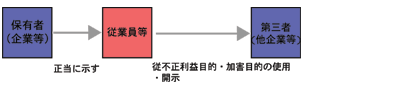
2条1項8号類型
その営業秘密について不正開示行為(前号に規定する場合において同号に規定する目的でその営業秘密を開示する行為又は秘密を守る法律上の義務に違反してその営業秘密を開示する行為をいう。以下同じ。)であること若しくはその営業秘密について不正開示行為が介在したことを知って、若しくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得し、又はその取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為
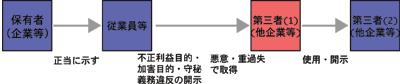
2条1項9号類型
その取得した後にその営業秘密について不正開示行為があったこと若しくはその営業秘密について不正開示行為が介在したことを知って、又は重大な過失により知らないでその取得した営業秘密を使用し、又は開示する行為
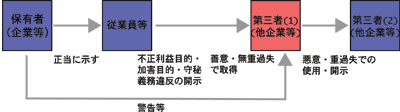
5)効果
・差止請求、損害賠償請求(3条〜8条)
(参考)民事訴訟法92条(秘密保護のための閲覧等の制限)
2.実務上の諸問題
1)秘密管理性の欠如
a.アクセス制限の欠如
・営業秘密と他の一般情報との区別がなされていない。
・営業秘密の保管場所が特定していない。
・ネットワークにパスワードを設定されておらず、アクセスについて人的・時間的制限がない。
・秘密保持契約(NDA)を結んでいない。
・社内において営業秘密の管理者が定められておらず、営業秘密の管理教育がなされていない。
b.客観的認識可能性の欠如
・「マル秘」「部外秘」等、機密事項である旨の表示がない等
2)競業避止義務の範囲・限界
退職後に退職者に対して競業避止義務を課す特約は、競業避止義務を課すべき必要性があり、競業行為の禁止の内容がその必要性を満たすために必要最小限度に止まっており、かつ、十分な代償措置がとられていることが必要である。
具体的には、退職後に退職者に対して競業避止義務を課す特約は、ア競業避止義務を課すべき必要性があり、イ競業行為の禁止の内容がその必要を満たすために必要最小限度に止まっており、かつ、ウ十分な代償措置がとられている場合にはじめて、その合理性を有するとされる(東京地裁平成13年8月27日判決など)。
3)営業秘密の取得、保護、管理
・従業員を中途採用する場合、前勤務先での業務内容項目、競業禁止義務・秘密保持義務等の有無、他社へ譲渡した発明・考案のリストなどにつき、聴き取り調査を行い、場合によっては、前勤務先に対し照会を行い、その内容を確認しておく。その上で、当社及び他社の営業秘密その他の知的財産を侵害してはならないこと、侵害した場合の法的制裁などについて説明し、その理解を得ておく。
・退職時に、保管資料の返還を受け、従事した業務、知り得た営業秘密、職務発明、保管資料、退職理由、転職先などを確認し、義務及び法的制裁などを告知しておく。また、営業秘密の漏洩がなされないように、誓約書も徴求しておく。