1.はじめに
a 企業を取り巻く環境の変化
ハードウェア(高機能化、大容量化)
ソフトウェア(多種、多機能化)
通信環境(ブロードバンド)等の飛躍的変化
ITリテラシーの向上
↓
ユビキタス社会の誕生
高度情報通信ネットワーク社会の形成
(IT基本法)
↓
・新しいビジネスモデルの誕生、ボーダレスエコノミー
(権利侵害範囲の拡大)
・「デジタル革命は究極のアナログ革命である」
(中谷巌)
b 企業を取り巻く各種リスク
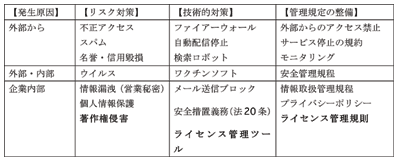
c 実務において考慮すべき諸要素
・コンプライアンス(遵法)経営の要請
・機会費用(opportunity cost)、訴訟コスト、「選択の自由」を考えた経済的合理性
・無申告加算税や懈怠税、鉄道営業法に見られる公平概念、契約における違約金条項
・知的財産立国を目指すための制度設計、メンタリティの醸成、向上
2.著作権侵害に基づく損害賠償請求
a 著作権侵害の法的効果
1) 民事責任
[1]差止請求(法112条)
[2]損害賠償請求(民法709条、710条、損害額の推定等法114条等)
[3]不当利得返還請求権(民法703条)
[4]名誉回復等の措置を受ける権利(法115条、民法723条)
2) 刑事責任
・懲役3年以下又は罰金300万円以下に処せられる犯罪行為(法119条1号)。
・2001年(平成13年)1月1日以後、法人の代表者(法人格を有しない社団又は財団の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して1億円以下の罰金刑が科される(法124条1項1号)。
3) 両責任の関係
・ 民事責任と刑事責任の完全分離思想
4) 著作権法114条の位置づけ
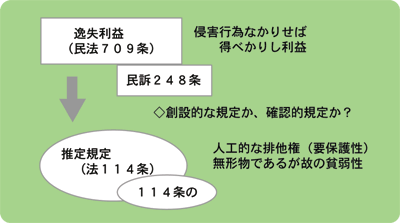
2.損害賠償論
1) 損害賠償とは
損害賠償とは,他人に与えた損害を填補することである。損害賠償の目的は,アリストテレスの挙げる正義の基本理念のひとつである矯正的正義(平均的正義)であり,被った損害に等しい賠償を与えるという原理である。損害賠償の内容をどのように定めるかは,何らかの理論に従って論理的に導かれる問題というより,すぐれて政策的な問題であり,同時に,国民感情や法意識によって左右される問題でもある(内田貴「民法2 債権各論」東京大学出版会379頁)。
2) 問題の所在
従来、民法においては、損害とは、不法行為がなかったとした場合における被害者の財産的・精神的状態と、不法行為により現実にもたらされた財産的・精神的利益状態の差であると言われている(いわゆる「差額説」、「填補賠償説」)。
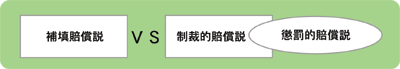
もっとも、「填補賠償説・制裁的賠償説の双方に共通するものであるが、理論が理論(理論的美学)のみに関心を示し、その理論が損害賠償額の算定と必ずしも結びついていないきらいがある」(田井義信「制裁的賠償説」現代不法行為法学の分析 有信堂p.159)
・“日本では、懲罰的損害賠償は認められていない”というドグマによって思考停止? cf.慰謝料請求(京都地判平成元年2月27日、判時1322号125頁)
・「不法行為制度は,発生した損害を填補し,原状を回復することにより被害者を救済するところにあるところから,仮に事後において違反者に対して提訴しても,当初より適切に著作物の使用料を支払っていた利用者と同程度の負担しか侵害者が負わないとすれば,侵害のやり得ということになり,違法行為への抑止力が働かないという議論がなされている」(作花文雄「詳解著作権法」(第2版)ぎょうせい470頁)
3) 懲罰的損害賠償
a) 最高裁判決
英米法のおける懲罰的損害賠償については、補償的損害賠償として約42万ドル,懲罰的損害賠償として約112万ドルの支払いを命じた外国判決の執行判決請求事件(民事執行法24条)に関し,最高裁は,「我が国の不法行為に基づく損害賠償制度は,被害者に生じた現実の損害を金銭的に評価し,加害者にこれを賠償させることにより,被害者が被った不利益を補てんして,不法行為がなかったときの状態に回復させることを目的とするものであり(最高裁昭和63年(オ)第1749号平成5年3月24日大法廷判決・民集47巻4号3039頁参照),加害者に対する制裁や,将来における同様の行為の抑止,すなわち一般予防を目的とするものではない」「我が国においては,加害者に対して制裁を科し,将来の同様の行為を抑止することは,刑事上又は行政上の制裁にゆだねられているのである。そうしてみると,不法行為の当事者間において,被害者が加害者から,実際に生じた損害の賠償に加えて,制裁及び一般予防を目的とする賠償金の支払いを受け得るとすることは,右に見た我が国における不法行為に基づく損害賠償制度の基本原則ないし基本理念と相いれないものである」(平成9年7月11日,民集51巻6号2573頁,判時1624号90頁)。
b) 立法段階での議論
「著作物が無断で利用された場合における著作権者の損害額が、通常の使用料相当額であり、無断で利用した者の支払うべき額と事前に許諾を得た者のそれとが同額であるというのは適当ではない。無断利用者に対しては、制裁的に、通常の使用料より多い額を請求し得るよう措置する必要がある」(昭和39年12月12日著作権制度審議会第一小委員会審議)
昭和41年に発表された「著作権及び隣接権に関する法律草案」の段階では,権利者は侵害者に対し,「通常受けるべき金銭の額の倍額に相当する額」を損害額として請求することができるとされていたが,「通常生ずべき損害の額を建前とする民法上の原則との関係において倍額請求を規定する理論構成及び説得性の問題,通常の使用料額主義を採っている工業所有権法体系との均衡論,一般国民への著作権思想の普及度の低さなどから,将来の検討課題として見送られた」(加戸守行「著作権法逐条講義〔三訂新版〕」著作権情報センター633頁)
c) 学説
・ 「私にとっては,この法律において一番心残りのところでございまして,いつの日にか法律草案の倍額主義思想が著作権法において実現することを心ひそかに期待しております。」(加戸633頁)
・ 特許法102条の解釈論について,「現在のわが国不法行為法を前提とする限り,アメリカのような制裁的機能の極めて強いトリプル・ダメージ(三倍賠償)あるいはピュニティブ・ダメージ(懲罰賠償)の制度を導入することは無理であろうが,無体財産権侵害の損害概念の構成次第では,制裁的色彩を多少加味することも不可能ではないであろう」(中山信弘「工業所有権法」弘文堂326頁)「ここにおける相当実施料とは,侵害時ではなく,裁判時における相当実施料と考えるべきであり,その間のすべての事情を考慮して決定すべきである。その意味から,ここにおける損害賠償は,規範的な意味を有すると言うべきであろう」(同322頁)
・ 「制裁、予防機能という観点のみからの立論では、より高額の損害賠償額を認めるとの主張は可能にはなっても、その額がいったい幾らで止まるのかを論じることは困難」(田村善之「知的財産権と損害賠償」弘文堂123頁)
4) 旧著作権法114条の規定
1侵害者の利益額=損害額(推定規定)
「著作権者,出版権者又は著作隣接権者が故意又は過失によりその著作権,出版権又は著作隣接権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において,その者がその侵害の行為により利益を受けているときは,その利益の額は,当該著作権者,出版権者又は著作隣接権者が受けた損害の額と推定する。」(同条1項)
2通常の使用料相当額→最低限の損害賠償額として保証(法定規定)
「著作権者又は著作隣接権者は,故意又は過失によりその著作権又は著作隣接権を侵害した者に対し,その著作権又は著作隣接権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額を自己が受けた損害の額として,その賠償を請求することができる。」(同条2項)
3通常の使用料相当額を上廻る損害賠償請求
「前項の規定は,同項に規定する金額をこえる損害の賠償の請求を妨げない。この場合において,著作権又は著作隣接権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは,裁判所は,損害の賠償の額を定めるについて,これを参酌することができる。」(同条3項)
5) 2項の使用料相当額(established royalty,reasonable royalty)
a)「通常受けるべき金銭の額」の認定方法
1著作物使用料規程によるもの
2権利者の許諾の例によるもの
3業界慣行等一般的相場によるもの
b) いくつかの裁判例
・ゴールデンミカド事件(大阪高判昭和45年4月30日,判時606号40頁)
著作権使用料を,著作物の利用の態様に照らし特に必要であると認められる場合に限り,契約の促進又は管理の効率化を図るため,減額することができ,著作物使用料規程により算出された「正規の額」が「通常受けるべき額」として,誠実に事前に使用許諾を求めてくる者と無断使用者を同等に扱う必要はないとの立場をとったとされる事例
・にほんの館事件(福岡高判昭和57年1月27日,判タ462号169頁)正規の使用料と減額された契約使用料という二元性を使って巧妙な形で損害賠償の制裁的機能が果たされてきた1例(百選203頁,松川実教授評釈)
・魅留来事件(大阪地判平成6年3月17日,判タ867号231頁)
「包括的使用料許諾契約の使用料は,事前に原告の許諾を受けた誠実な利用者のみに対する特別の優遇措置であり,同被告らのような無許諾の侵害者に対して適用されないことは同規程に明定されているところである」
6) 旧著作権法114条2項の改正(平成11年法律第77号)
a) 「通常」の文言削除
「通常受けるべき金銭の額」とされていたものについて,「通常」の文言を削除し,個別的事情を勘案した裁判所の裁量を認めることとした。
b) 立法趣旨
「既存の使用料規程等が参酌されることが多く,,,同じ額を賠償すればよい結果となり,いわゆる『侵害し得』の状況が生じる,,,当該事件の具体的事情を考慮した『相当』な使用料の認定ができることとすることが適当である。この場合,『相当』な使用料とは,当事者間の業務上の関係や侵害者の得た利益等,侵害者と権利者との間の様々な事情を考慮して決定する,実情にあった使用料という意義を有することとなる」(文化庁著作権審議会第1小委員会専門部会(執行・罰則関係)報告書(平成11年12月))
c) 学説
・「受けるべき金銭の額に相当する額」の算定に当たり、使用許諾を受けて使用している者と、使用許諾を受けずに無断使用している者とを、必ずしも同一に論じる必要はない(紋谷暢男・著作権判例百選(第二版)209項)
・「侵害行為が行われた場合に,法の趣旨を貫徹するために,市場機会の利用可能性の侵奪をもって損害と観念し(規範的損害概念の設定),市場機会の著作権者によっての利用価値を賠償額とする規定である」「侵害者の利益額を参酌した,より高額の対価をもって2項の賠償額としなければならない(さもないと簡便な強制許諾の請求権を侵害者に与えることになりかねない)」(田村善之「著作権法概説」(第2版)有斐閣328頁,330頁)。
3.パッケージソフトに関する裁判例(旧法)
a関係図
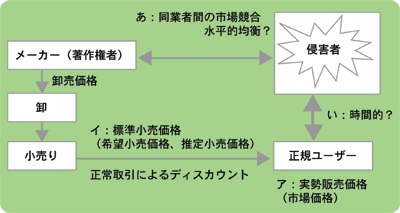
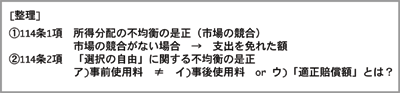
bLEC事件(東京地判平成13年5月16日、判時1749号19頁)
1) 事案の概要
ソフトウェアメーカー3社が、司法試験等の受験指導を行う会社に対し、企業内でプログラムを違法にインストールして使用したことが著作権侵害に該当するとして、プログラムの使用差止及び損害賠償を認めた事案(「Incongnito」を使用し、シリアル番号検索機能を停止させていた事情もあり)。
2) 当事者の主張
●使用許諾料こそは、まさに、著作権の行使によって通常受けるべき金銭の額であることは、広く認められた慣行であり、かつ法の規定である
○違法コピーに関しては、侵害者との間で多数の和解契約を締結しているが、全て正規品小売価格を上回る金額を基準として行われている
○一曲一回の「使用料」が包括的使用許諾契約に基づく使用料の6.28倍となるケースについて、東京地裁は、金額の違いも不合理であるとまではいえない」(平成12年11月28日)と判示しており、実質的には同一の発想である
●2倍以上が相当との根拠が懲罰目的ないしは、無断複製防止目的をその論拠とし、むしろ、政策的見地に依拠しているもの
○2倍相当額は、損害賠償額として相当な額であり懲罰的賠償ではない
○著作権法114条1項による算定
ア:本件プログラムを違法に複製したことにより、正規に購入したら支出すべき本件プログラムの正規品価格を支出しなかったという利益を受けている、イ:被告の業務にもっぱら本件プログラムの使用が寄与したものということができ、被告の売上高が153億円(平成11年3月期)であることなどから、被告が本件プログラムの侵害行為から得た利益額は、金5000万円を下らない
●使用許諾者に発生する損害とは、本来なら前払を必要とされる一括払料金が回収できないことによる同料金相当額のみである
●損害額の算定に当たっては、標準的割引率を適用した卸売価格によるべき
○卸売価格で算定しなければならないとすると、正規に購入している者よりも安く使用できることになり著しく不合理
●侵害者が支払いを免れている市場価格が適用されるべきものである
○損害額の算定にあたっては、割引価格ではなく正規品小売価格によるべき。標準的割引率は、一定の条件を満たした顧客にのみ適用される特典であり、違法にソフトウェアをコピーした者に対しては割引価格は適用されない。また、通常、割引率は、大量に購入することによって大きくなるが、大量に違法コピーした者が得をするというのは、著しく不合理
3) 判示事項
「侵害行為によって得た被告の利益額は,別紙侵害品目録1ないし3記載のとおり,無許諾複製したプログラムの数に正規品1個当たりの小売価格(価格は弁論の全趣旨により認める。)を乗じた額であると解するのが相当である。」
「そして,原告らの受けた損害額は,被告の得た前記利益額と同額であると推定されるべきである。また,原告らの受けた損害額を許諾料相当額により算定すべきであるとした場合も,許諾料相当額はこれと同額であると解するのが相当である。」
「本件プログラムの無許諾複製によって被告の得た利益額は,正規品小売価格相当額により評価し尽くされ,これを超えると解するのは相当でなく,本件において,被告が違法複製品を使用した回数や期間を考慮するのは相当でないというべきである。したがって,原告らの受けた損害額は,正規品の小売価格相当額を超える額と推認することはできない。」
「本件のように,顧客が正規品に示された販売代金を支払い,正規品を購入することによって,プログラムの正規複製品をインストールして複製した上,それを使用することができる地位を獲得する契約態様が採用されている場合においては,原告らの受けた損害額は,著作権法114条1項又は2項により,正規品小売価格と同額と解するのが最も妥当であることは前記のとおりである。」
4) 検討
・この判決は、本年1月1日施行の著作権法改正(114条の4の新設など)により損害額の認定に関する裁判所の裁量権の範囲が拡張された大きな流れと一致するもの(岡邦俊JCAジャーナル第48巻7号45頁)
・「自己が案出した附合契約に損害賠償額の予定を定め、高額の違約罰を定めることによって、「もともと支払うべき料金を発覚したときに限って後払いすればよいだけだという不合理」を回避することができたのであり、そうした努力を怠った結果が権利者に帰するのは、むしろ当然のこと」「使用の頻度や期間に関わらずすべての顧客に一定額の対価を要求しているのであり、それは権利者自身の選択に過ぎない」(玉井克哉教授)
3.ヘルプデスク事件(大阪地判平成15年10月23日)
1) 事案の概要
原告らが、パソコンスクールを経営する被告会社による複製権侵害があり、代表者にもその職務を行うにつき悪意又は重過失があったとして、民法709条、商法266条の3に基づく損害賠償を請求した事案。
2) 判示事項
「原告らは、被告会社による本件プログラムの違法複製によって被った損害の賠償として、著作権法114条2項に基づく請求をする。
著作権法114条2項は、著作権を侵害した者に対し、著作権者は「著作権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額を自己が受けた損害の額として」その賠償を請求することができる旨定めているが、同項にいう「受けるべき金銭の額に相当する額」は、侵害行為の対象となった著作物の性質、内容、価値、取引の実情のほか、侵害行為の性質、内容、侵害行為によって侵害者が得た利益、当事者の関係その他の訴訟当事者間の具体的な事情をも参酌して認定すべきものと解される。そして、本件に現れたこれらの事情を勘案すると、本件においては、原告らが請求できる「受けるべき金銭の額に相当する額」は、本件プログラムの正規品購入価格(標準小売価格)と同額であると認めるのが相当である。
原告らは、原告らの「受けるべき金銭の額に相当する額」につき、ア:プログラムの違法複製による被害の甚大性、イ:被告会社の行為の高度の違法性、ウ:正規品の事前購入者との均衡、エ:社会的ルールの要請を根拠に、本件プログラムの正規品購入価格(標準小売価格)の2倍を下らない旨を主張する。
しかし、不法行為に基づく損害賠償制度は、被害者に生じた現実の損害を金銭的に評価し、加害者にこれを賠償させることにより、被害者が被った不利益を補てんして、不法行為がなかったときの状態に回復させることを目的とするものである。このことは、著作権侵害を理由として損害賠償を請求する場合であっても異ならず、著作権法114条2項の規定に基づき、著作権者が著作権を侵害した者に対し、「著作権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額を自己が受けた損害の額として」その賠償を請求することも、基本的に上記の不法行為による損害賠償制度の枠内のものというべきである。
このような観点から原告らの主張を検討すると、まず、原告ら主張のア:の点は、別個の損害(プログラムの違法複製を防止するための費用の支出)を、争点1で認定した損害の額の算定に含めようとするに等しく、相当ではない。イ:の点も、本件のようなプログラムの違法複製の事案においては、違法性が高度であるからといって、そのことが直ちに損害の額に反映される性質のものではなく、少なくとも、当該プログラムの正規品購入価格(標準小売価格)の2倍というような額の賠償を根拠付けるものとはいえない。ウ:の点も、市場における実勢販売価格より標準小売価格が高額であるのが一般であるから(なお、不法行為に基づく損害賠償の場合は、別途不法行為時からの遅延損害金も加算される。)、直ちに正規品の事前購入者との均衡を失するものとはいえない。原告らの主張を、加害者に対する制裁や将来における同様の行為の抑止(一般予防)を目的とするものと解しても、不法行為による損害賠償の制度は、直接にそのようなことを目的とするものではない。エ:の点も、プログラムの違法複製について、原告らの主張(プログラムの正規品購入価格より高額の金銭を支払うべきものとすること)を根拠付けるような実定法上の特別規定があるわけではないし、そのような内容の社会規範が確立していると認めるべき証拠もない。原告らの主張はいずれも採用することができない。
一方、被告らは、原告らが「受けるべき金銭の額に相当する額」(著作権法114条2項)とは、卸売価格相当額である旨を主張するが、違法行為を行った被告らとの関係で、適法な取引関係を前提とした場合の価格を基準としなければならない根拠を見い出すことはできない。この点に関する被告らの主張は採用することができない。
以上のとおり、原告らが「受けるべき金銭の額に相当する額」(著作権法114条2項)としては、本件プログラムの標準小売価格を基準として算定すべきである。原告らは、予備的に、著作権法114条1項に基づく損害賠償額の算定も主張するが、その主張に係る具体的金額が標準小売価格にとどまり、同条2項による場合の認定額を上回るものではないから、判断する必要をみない。」
4.結びにかえて
a 知的財産権における適正なバランス
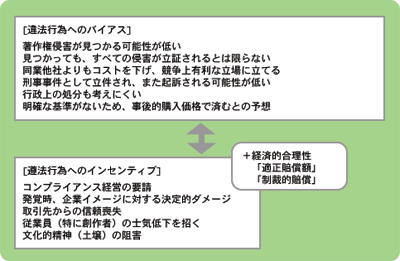
b 議論の動向
・「文化審議会著作権分科会報告書」の概要(2004年1月14日答申)
・損害賠償制度の見直しに係る論点の整理
c 知的財産権に関する損害賠償論
・ 恥の文化(ルース・ベネディクト「菊と刀」)に頼るのではなく、21世紀に相応しい知的財産に関する新しい制度設計や解釈論を考えるべき
・ 著作権侵害という違法行為が行われた場合、正規ユーザーとの実質的公平の観点から、事前の正規ユーザーが負担する使用料とは異なる事後的観点から「適正賠償額」を考えるべき
・ 小売店における割引金額の差額だけでは不十分であり、「適正賠償額」は,正規品購入価格よりも十分に高い金額でなければならない
・ 権利者の負担となる無形の機会費用、訴訟コストなども考慮し、経済的合理性が認められる「適正賠償額」を考えるべきであり、「制裁的」であるという理由のみで否定すべきではないcf.ヘアーブラシ事件「無形損害」(大阪地判昭59年12月20日無体集16巻3号803頁)
・ 「適正賠償額」を観念しなければ、違法行為へのバイアスを解消することはできず、到底、著作権法の目的である「著作権者等の権利保護」や「文化の発展」を図り得ない。
|



