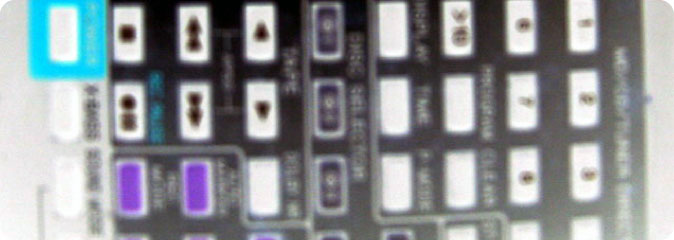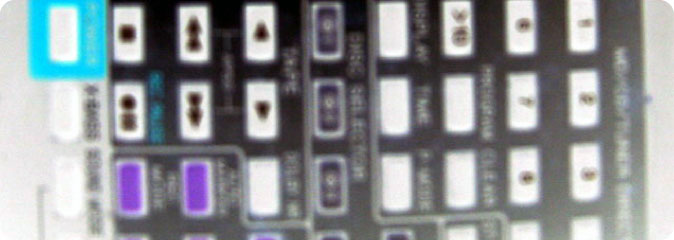1.デジタルデータの証拠能力
民事裁判においては、当事者が自白した事実及び顕著な事実以外の事項については、証拠により証明しなければならず(民訴法179条)、的確に証拠を提出できるかどうかによって訴訟の勝敗が決せられると言っても過言ではありません。そこで、デジタルデータが、訴訟においてどのように扱われるのかという点がここでのテーマです。
民事訴訟法における立法例として、証拠として提出すべきものには一定の制限が課す考え方(法定証拠主義)もありますが、日本の民事訴訟では、「自由心証主義」(民事訴訟法247条)が採用されておりますので、原則として何を証拠として提出することもでき(証拠方法の無制限)、その上で、提出された証拠に証拠価値を認めるかどうか、証明力をどう評価するかについては、すべて裁判官の自由な判断に委ねるとされています。
ですので、デジタルデータであっても、証拠能力は認められ、裁判所に証拠として提出することができることになります。
2 証拠法上の取扱い
次に、デジタルデータの証拠法上の取扱について、参考になる裁判例として、文書に準じるものとして扱うべきであると判示したものがあります(大阪高決昭和53年3月6日高民31巻1号38頁・・判時883号9頁)。このケースは、文書提出命令に関するケースですが、デジタルデータを電磁的に記録した磁気テープは旧民事訴訟法312条の文書に準ずるものというべきであるとするとともに、磁気テープの提出を命じられた者は磁気テープを提出するのみでは足りず、その内容を紙面等にアウトプットするのに要するプログラムを作成してこれを併せて提出すべき義務を負うとしています。
ただ、デジタルデータを書証(民訴法219条)と全く同視することはできず、次の点に留意する必要があります。
まず、書証の場合には、日本の民事訴訟法の228条4項によって、私文書に本人または代理人の署名または捺印があれば、真正に成立した文書であるという推定を受けることになっていますが(形式的証拠力)、電子署名及び認証業務に関する法律3条に基づく電子署名が行われている場合を除き、デジタルデータの場合には、このような推定を受けられないということになります。
次に、書証の場合には、原本、正本もしくは認証のある謄本(コピー等の複写)なのかどうかが明確であるのに比べ、デジタルデータの場合には、その特質上、何が原本であるのか、必ずしも明確ではありません。さらに、紙媒体に情報が固定されている書証と比べて、デジタルデータの場合、容易に改竄することができ、その上改竄の痕跡も残らないため、当初の情報内容をそのまま有しているのか、その信用性についての問題があります(実質的証拠力)。
3 実務的対応
現在の裁判実務では、便宜的な取り扱い方法として、デジタルデータをプリントアウトして、それを書証の原本として提出するという取り扱いが認められています。もっとも、原本として取り扱うとしても、プリントアウト結果がデジタルデータのもともとの内容と必ずしも同一であるとは限らず、また、もし同一であったとしても、改竄の可能性が存する以上、安易に信用することはできず、注意が必要です。
また、時間の先後関係が重要になるなどの場合には、公証役場において、デジタルデータをプリントアウトした書面に、確定日付の付与を受けておくという対応や、今後、電子署名及び認証業務に関する法律に基づく電子署名を利用した認証方法を活用したりすることも考えられます。