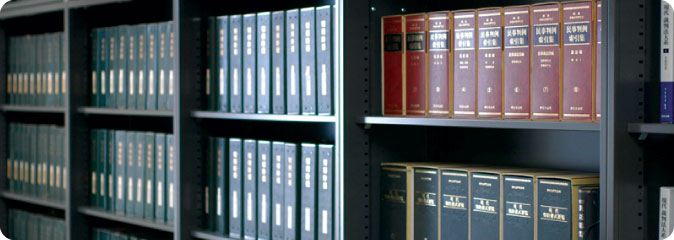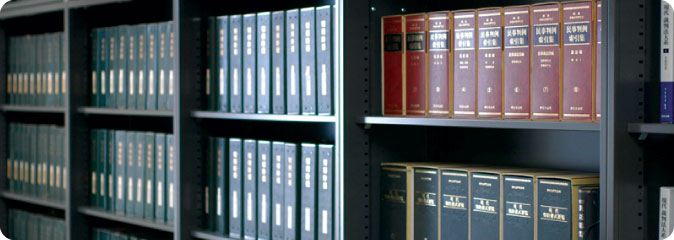日本最高の啓蒙思想家である福沢諭吉先生は、「学問のすすめ」(岩波文庫)において、生来平等な人間に差異をもたらす学問の意義について論じています。すなわち、「賢人と愚人との別は、学ぶと学ばざるとに由って出来るものなり」「天より定めたる約束にあらず」としています。そして、「専ら勤むべきは人間普通日用に近き実学なり」として、実学の重要性を説くとともに、「学問をするには分限を知ること肝要なり・・・その分限とは、天の道理に基づき人の情に従い、他人の妨げをなさずして我一身の自由を達することなり」(13p)という注意も行っています。
さらに、「方今我国の形勢を察し、その外国に及ばざるものを挙ぐれば、曰く学術、曰く商売、曰く法律、これなり。世の文明は専らこの三者に関し、三者挙らざれば国の独立を得ざること識者を俟たずして明らかなり。然るに今我国において一もその体を成したるものなし」(37p)と論じていますが、現代の日本において、その三者は、外見的には形式が整えられていると言えなくもありませんが、果たして世界的に評価され得る真の学術やグローバル経済に耐えうる商売、あるいは、人々の間に法の精神が育っているかというと甚だ疑問と言わざるを得ません。
私は、これまで、いくつかの大学の非常勤講師を務めるとともに、社会人相手の各種講演を数多く行ってきましたが、時には、高校生や小学生を相手に、法律学や弁護士の仕事に関する課外授業や法廷傍聴等も数多く行ってきました。日本がこれから真の文明国家として歩んでいくためには、学問や教育の問題を避けて通ることはできません。そして、実際の経済社会や当事者に接し、社会紛争の現場を知っている弁護士こそ、その実学の精神や知識、経験を学生に伝えていくべき任務を負っている職業の一つではないか、そう考えており、そのための努力は惜しまないつもりでいます。